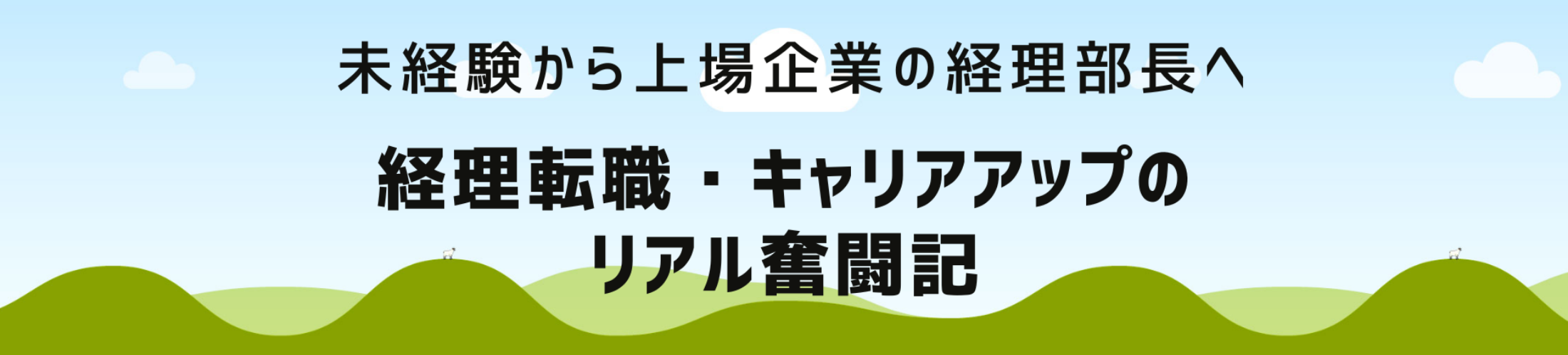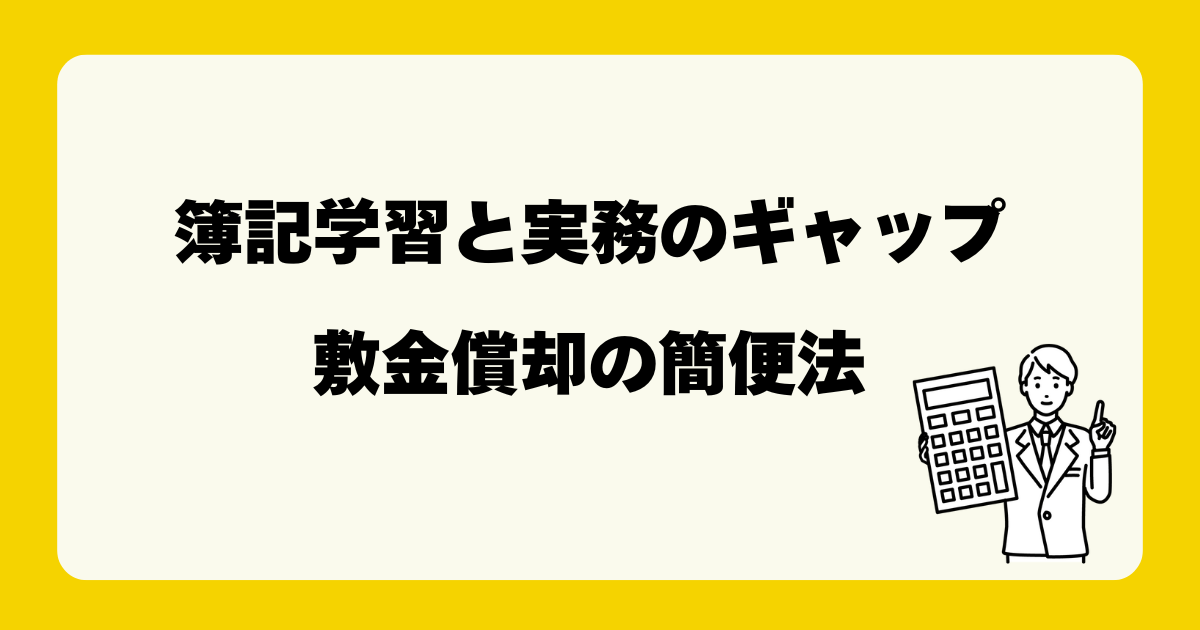簿記を取得後、経理業務を行う中で、
「簿記で勉強したことと違うな。。。」
と感じる場面があります。
その要因のひとつが「会計処理の簡便法」ですが、今回は敷金に関する簡便法について解説します。
簿記を勉強していた人からすると、「資産除去債務」の出番だな!とやる気になりますが、簡便法では、資産除去債務を使用せず会計処理をします。
なお、会計処理を変更する場合は、会計監査人と事前にしっかりとすり合わせをしましょう!
敷金の簡便法とは?
オフィスを借りた場合、賃借契約において、当該賃借建物等に係る有形固定資産(内部造作等)の除去など、原状回復をすることが契約で要求されていますので、当該有形固定資産に関連する資産除去債務を計上しなければならない場合があります。
原則法では、資産除去債務の算定、見積もりの変更、割引計算など、実務上は一定負担がありますので、簡便法が認めらえるケースがあります。
建物等の賃借契約において、当該賃借建物等に係る有形固定資産(内部造作等)の除去などの原状回復が契約で要求されていることから、当該有形固定資産に関連する資産除去債務を計上しなければならない場合がある。この場合において、当該賃借契約に関連する敷金が資産計上されているときは、当該計上額に関連する部分について、当該資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する(「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」9項)。
資産除去債務に係る実務負担を考慮し、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されている場合には、当該計上額に関連する部分について、当該資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上する方法によることができることとした(「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」27項)。
敷金の簡便法を使うメリット
敷金の簡便法を使うことのメリットは、細かな計算が省略できるため、「業務の負担が減少」、及び「ミスの減少」が挙げられます。
実際の会計処理の流れ
では、実際に敷金の簡便法をどのように使うのか、具体的な処理方法を見ていきましょう。
1. 前提条件
A社(自社)はB社との間でC建物の賃貸借契約を締結し、2024年4月1日から賃借をしている。
また、A社は契約と同時に10,000を、B社に敷金として支払いを実施。Z社の決算日は3月31日である。A社の入居期間は 5 年と想定。
2. 会計処理
(1)2024年4月1日
賃貸借契約を締結した際に、借主から敷金を受け取ります。このとき、敷金を「預り金」として計上します。仕訳は次のようになります。
敷金 10,000 /預金 10,000
(2)2025年3月31日
原状回復時の工事の見積りを取得したところ、敷金のうち6,000について原状回復費用に充てることが必要になり、6,000については返還が見込めないと認められたことから、入居の見積り期間である5年で費用配分することとした。
敷金の償却 1,200 /敷金 1,200
簡便法の注意点
簡便法を使う際にも、いくつか注意すべき点があります。
- 原状回復の見積金額の確認:原状回復費用の見積額が敷金計上額を上回る場合には敷金で資産除去債務を負担しきれないため、簡便法の適用は難しいかと思います。
- 見積項目について会計監査人とすり合わせ:「敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額」や「入居期間」により償却する金額が変動しますので、見積りの根拠を事前に会計監査人とすり合わせるとよいでしょう。
- 税務上の取扱い:会計上は敷金の償却額は費用計上しますが、税務上は、債務確定基準の観点から、原則として損金不算入となります。顧問税理士と連携をしっかりとしましょう。
まとめ
敷金の簡便法を使うことで、経理業務は大幅に効率化できます。特に経理初心者の方には、複雑な処理を避けるために有効な方法です。敷金を「預り金」としてシンプルに計上し、契約終了後の返金処理を簡素化することで、業務の負担を減らすことができます。
今後、経理業務を行う際には、敷金の簡便法をぜひ活用して、業務を効率的に進めていきましょう。