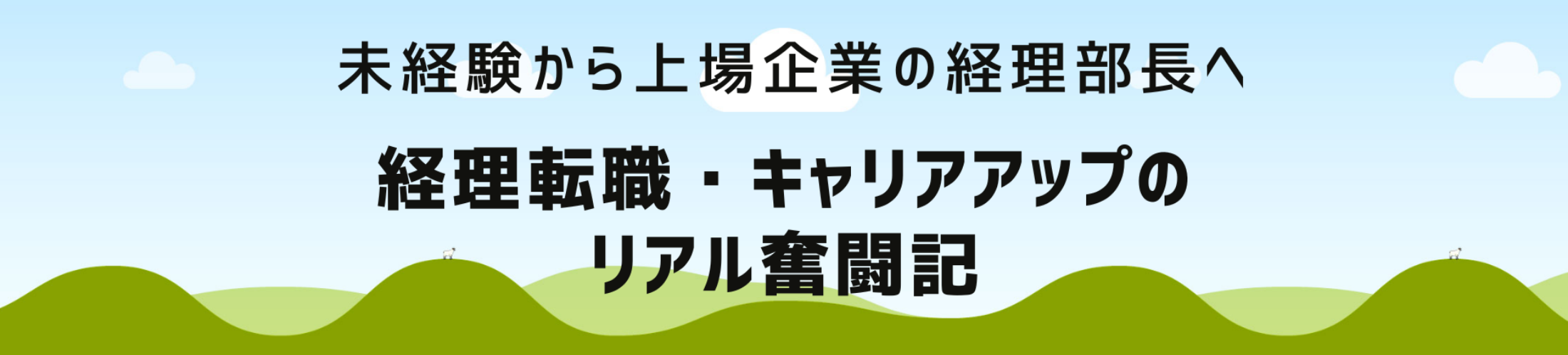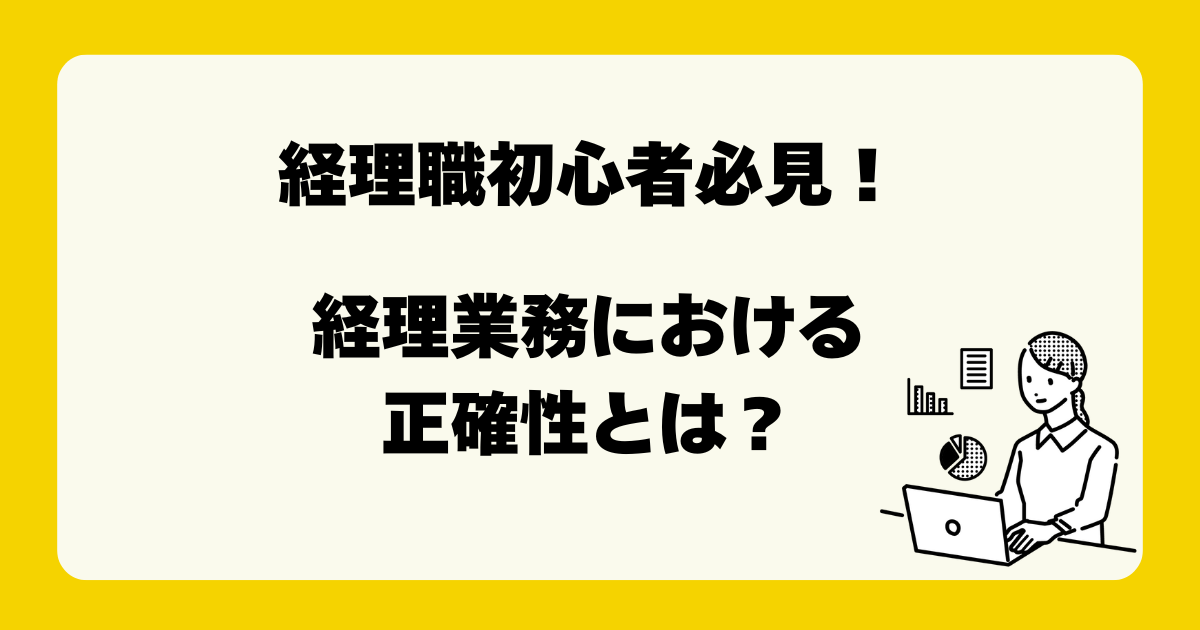経理のマネジメントの立場で、「信頼できる!」、「安心して業務を任せられる!」という経理メンバーが持つスキルのひとつに、「正確性」が挙げられます。
仕訳の入力が早くとも、ミスが発見されると、「他にもミスはあるかもしれない。。。」となり、チェックに工数がかかります。経営陣への業績報告、開示資料の作成など、数字のミスは会社の経営にも影響を与えるため、どんなに忙しくても、常に正確であることが求められます。
しかし、経理未経験者にとって、この「正確性」を担保する方法は、イメージが湧きにくいかと思います。そこで、今回は経理職に必要な正確性を保つための技術をわかりやすく解説します。
目次
正確性を担保するために必要な基本的な技術とは
経理の業務では、数字を入力(転記)したり計算したりする場面が多くありますが、その中で正確性を確保するために行うべき重要なステップがあります。具体的な方法をいくつか紹介します。
1. 仕訳入力後の異常値チェック
仕訳を入力した後、必ず試算表や月次推移に異常がないかを確認することが大切です。例えば、貸借対照表(BS)や損益計算書(PL)の数値の推移を見て、過去と比べて大きな変動がないかチェックします。異常値を早期に発見することで、ミスや不正を防ぐことができます。
- 具体例:
例えば、仕訳入力後に「前月は10,000円だった売上が今月突然30,000円になっている」という場合、急激な変動が正当な理由でない場合には入力ミスを疑うべきです。
2. タテヨコ計(行と列)の確認
Excelなどで計算を行う場合、タテヨコ計が合っているかを確認することも非常に重要です。タテ(行)とヨコ(列)の計算結果が一致していないと、入力ミスや計算ミスが疑われます。数字を再度確認することで、大きなミスを防ぐことができます。
- 具体例:
たとえば、経費の合計が「行」で合っていても、横の「列」では合っていない場合があります。これを確認せずにそのまま提出すると、ミスが見逃されてしまうことがあります。
3. 会計データと他の管理表との一致確認
会計データだけでなく、他の管理表や証憑との一致を確認することも正確性を担保する上で大切です。例えば、在庫管理表や給与明細といったデータと会計データを照らし合わせて、数値にズレがないか確認します。異なるデータが一致していない場合には、何か間違いが発生している可能性があります。
- 具体例:
たとえば、在庫管理表の在庫数と会計データの仕入れ金額が合わない場合、どこかに誤りがあると考え、再確認する必要があります。
4. ダブルチェックの習慣化
経理の仕事では、常にダブルチェックを行う習慣が重要です。自分でチェックするだけでなく、他のスタッフや上司に確認してもらうことを習慣化しましょう。これにより、見落としやミスを防ぐことができます。忙しそうにしている上司に確認を依頼するのは、気を遣ってしまう方もいるかもしれませんが、後でミスが発覚して資料を作り直す手間に比べれば、事前チェックの方がラクです。
- 具体例:
例えば、仕訳を入力した後に、自分の入力を他のスタッフに確認してもらい、問題がないかを確認してもらいます。これにより、見逃しがなくなります。
5. 自動化ツールの活用
自動化ツールを活用することで、ミスを減らすことができます。たとえば、会計ソフトの自動仕訳機能や、Excelの計算式などを使用して、手作業でのミスを最小限に抑えることができます。自動化ツールを使うことで、効率的に正確性を保つことができます。また、「転記」するということ自体がミスを生み出すもとにもなりますので、API連携などで会計ソフトと各ツールを連携させることが出来ると非常に業務効率化に繋がります。
- 具体例:
請求書管理ツールと会計ソフトをAPI連携することで、転記によるミスを減らし、確認作業を短縮できます。
まとめ
働く会社の規模や組織体制によって、変わる部分もあると思いますが、経理職に求められる「正確性」を保つためには、仕訳の確認や計算ミスのチェック、データの整合性確認など、日々の習慣が大切です。ダブルチェックや自動化ツールの活用も効果的な方法です。これらの方法を身につけることで、経理業務において正確性を確保し、ミスを未然に防ぐことができます。経理未経験者でも、これらのポイントを意識して実践することで、プロフェッショナルな経理スタッフとして活躍できるようになるでしょう。